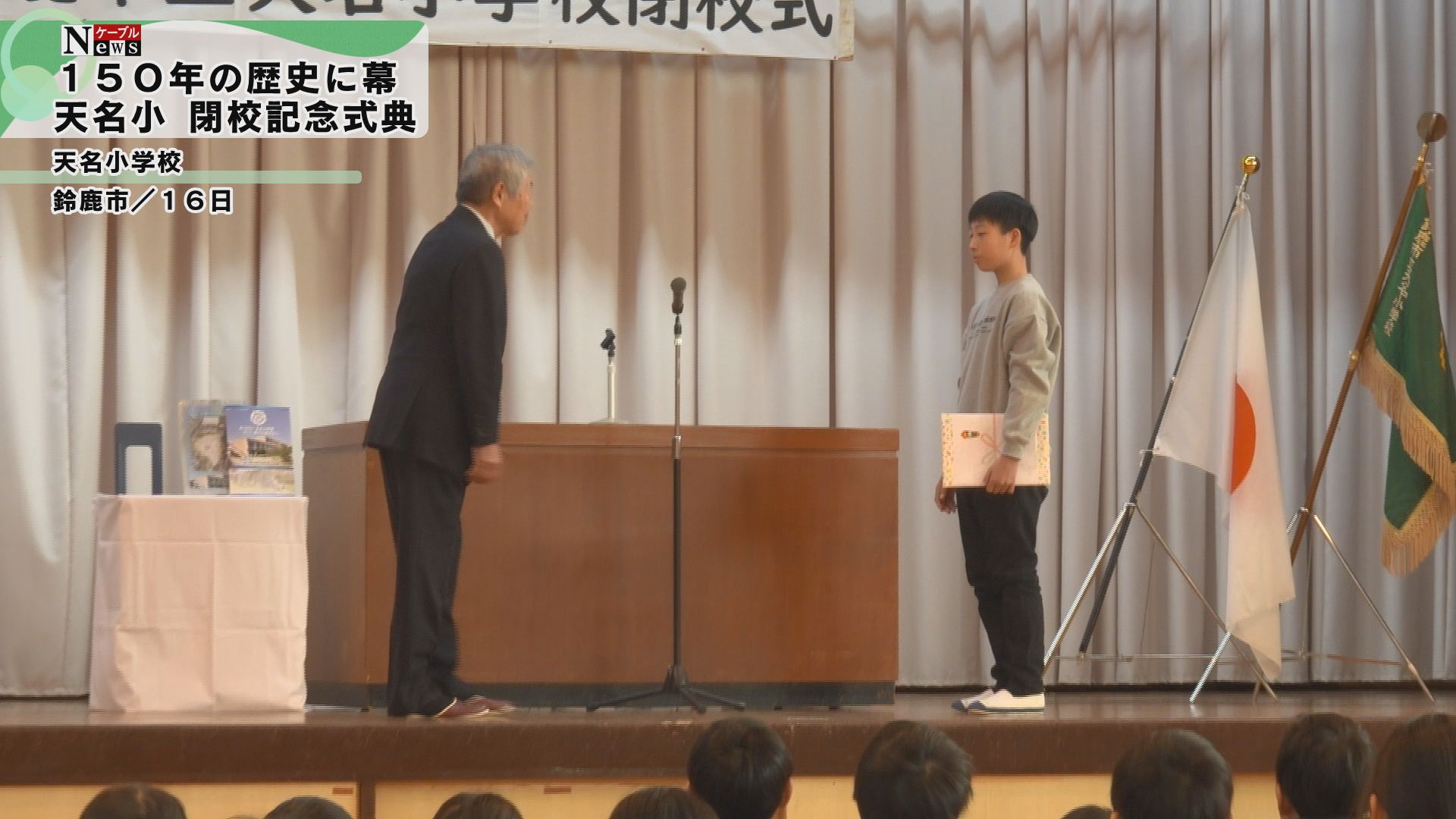四日市市立博物館では毎年、館長による定期講座を開いています。
今年度は、館長の毛利伊知郎さんが
専門分野の日本美術史をテーマに全3回行います。
初回となった22日は、
日本美術が海外の作品からどのような影響を受けてきたかを
講演しました。
毛利さんによると、日本美術の歴史は主に、
中国からの影響を受けた江戸時代以前のものと、
西洋からの影響を受けた明治時代以降のものに
分けて解釈できるということです。
中国 唐の時代、白・緑・褐色の
3色を使って焼かれた陶器、唐三彩。
日本では、奈良時代から平安時代にかけて
唐三彩を手本に、奈良三彩として独自に発展しました。
また、模様のついた紙、唐紙に
和歌をしたためることが流行したのも唐の影響です。
一方で、西洋文化の風は明治時代以降に広がり、
フランス留学の経験を持つ黒田清輝の作品がその代表例です。
黒田は、フランスの画家、ラファエル・コランに師事し、
西洋画の技法を学びました。
自然の光を活かした色彩表現から、柔らかさ、優しさが感じられます。
四日市市立博物館の館長講座は、来年1月と3月にも開かれます。
予約不要で参加費は無料です。