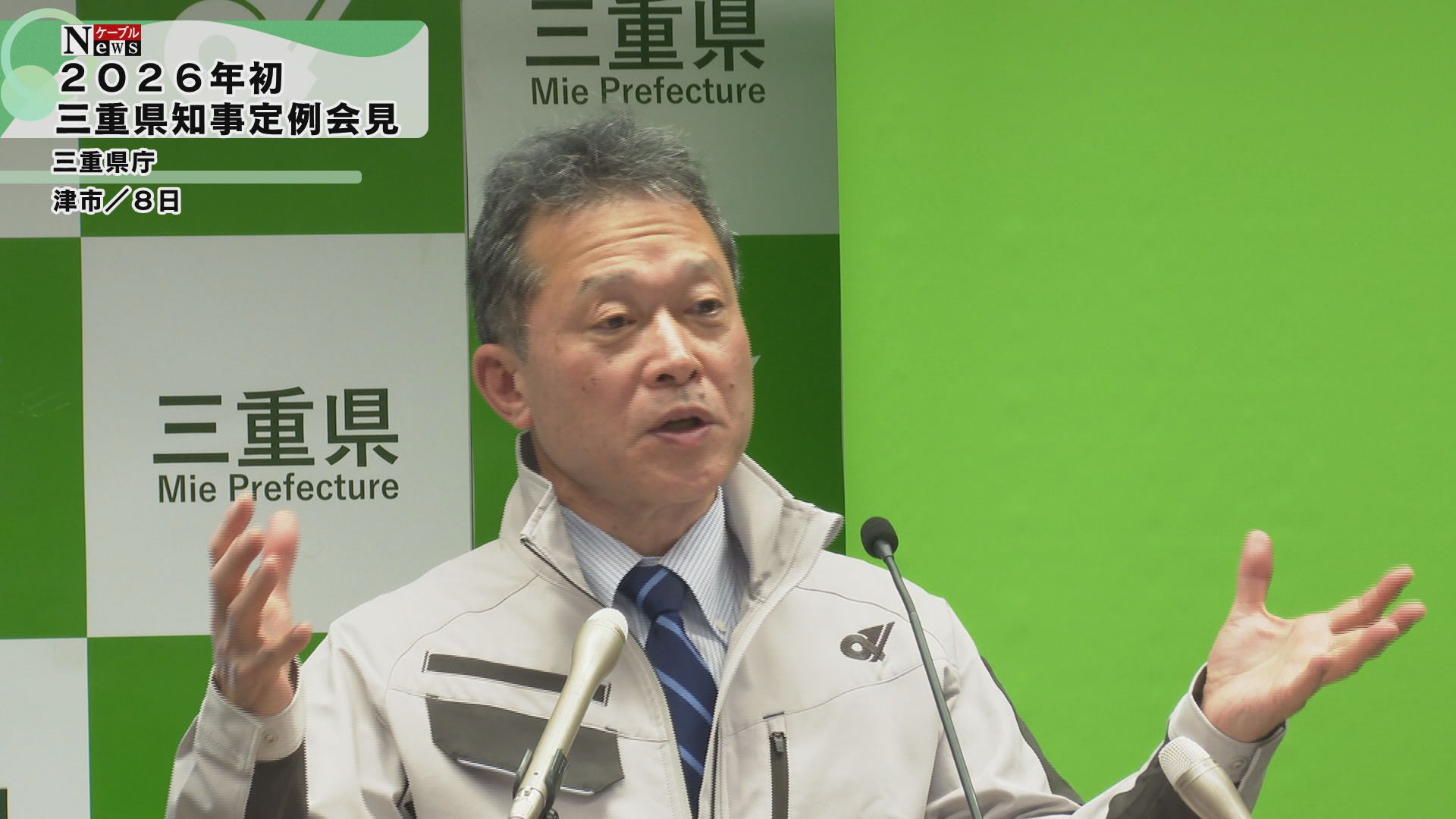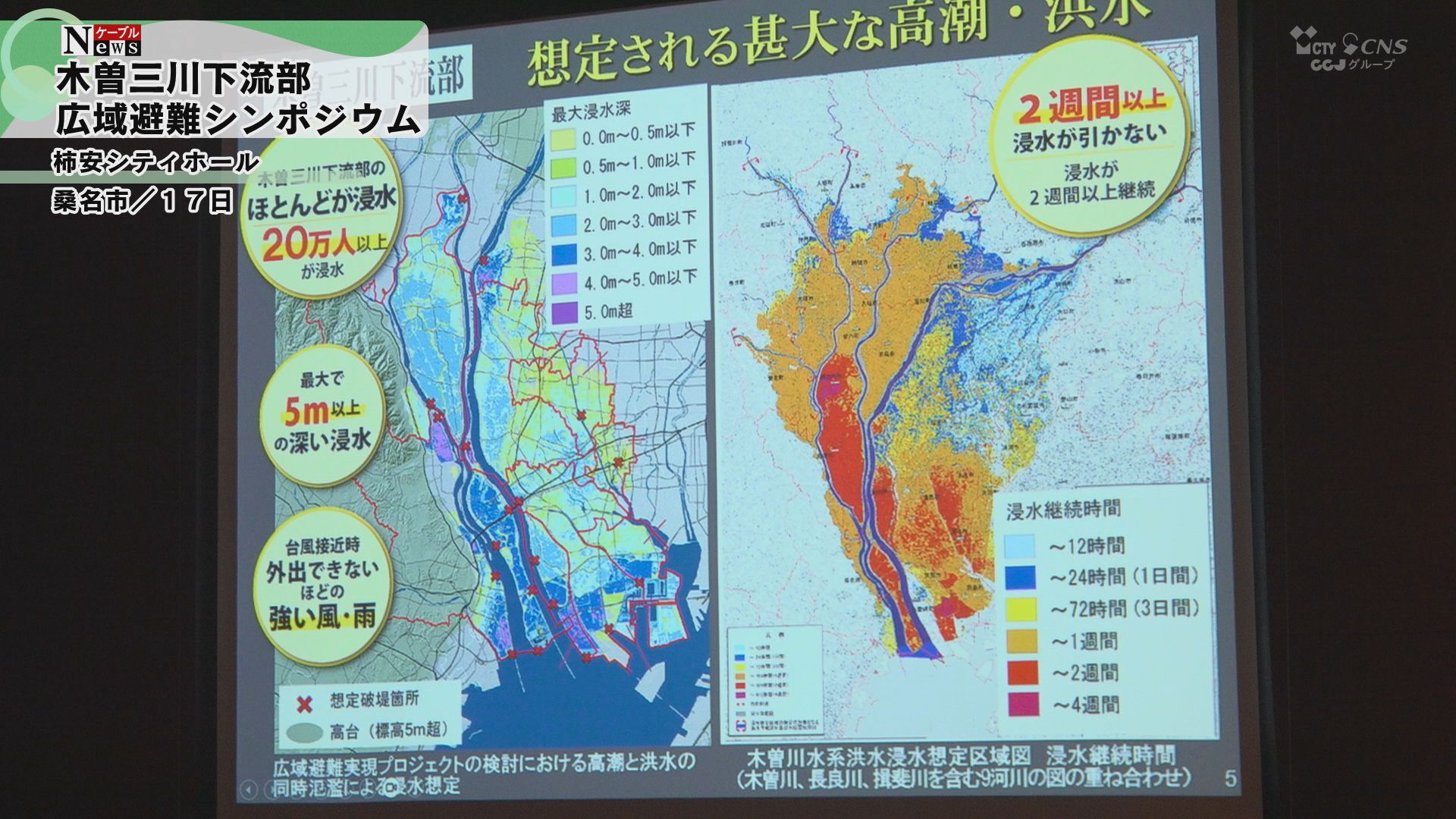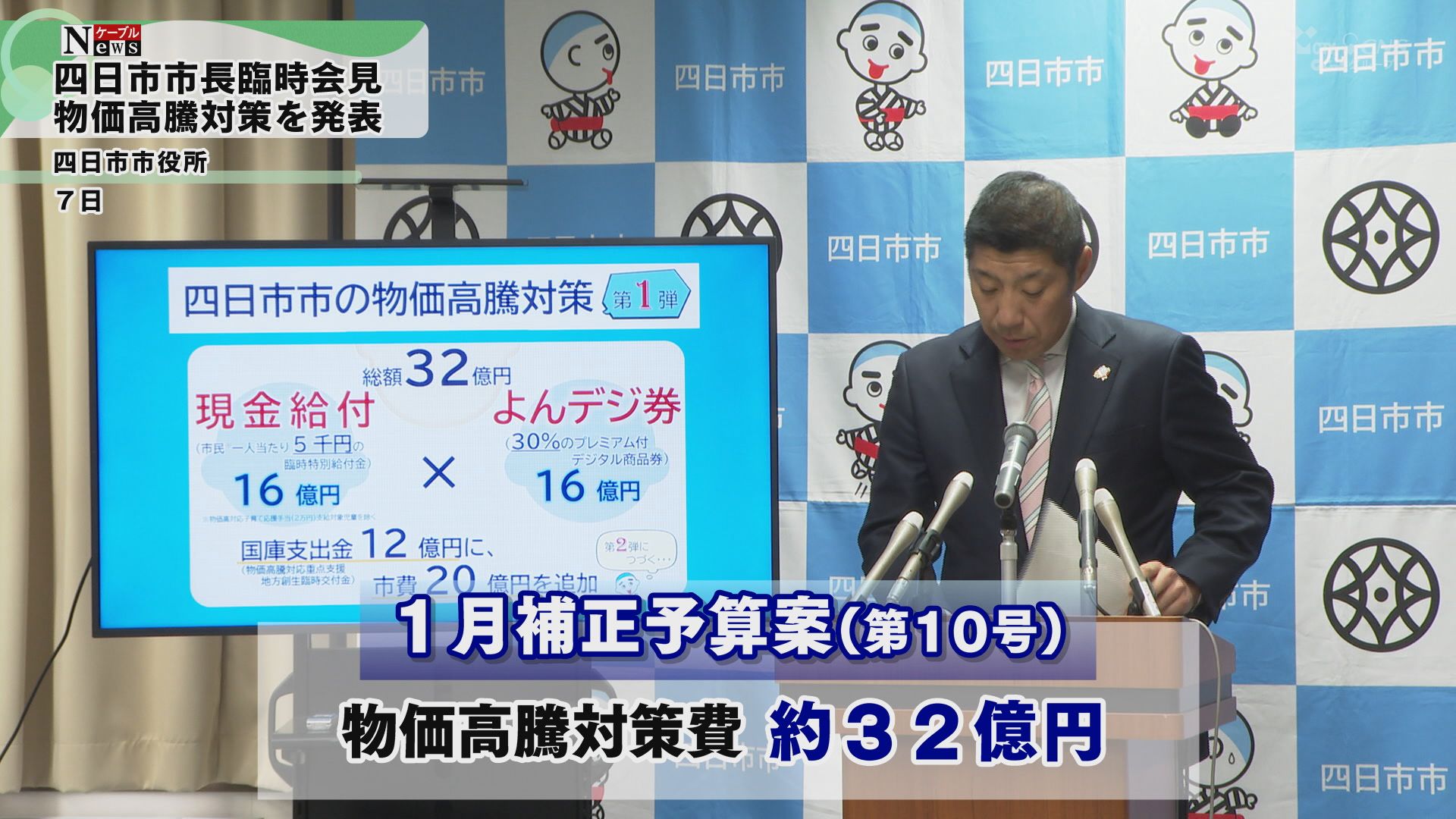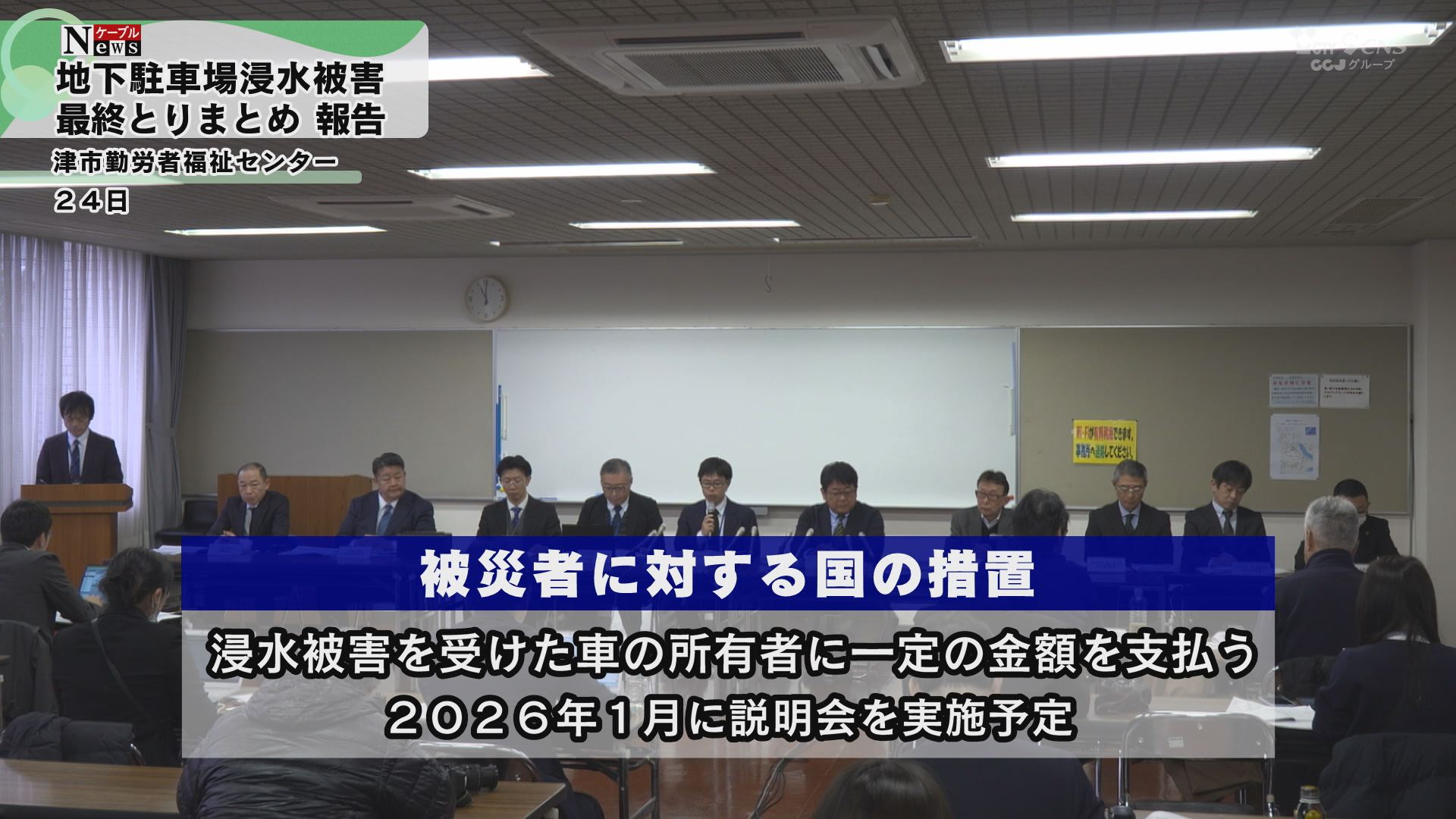ケーブルNews「戦争の記憶 80年目の今」のコーナーで
四日市市川尻町の正久寺を取材しました。
正久寺の境内に置かれている
コンクリートの梵鐘は、戦争に大きく関わっていました。

新しい梵鐘になるまで
コンクリートの梵鐘がつるされていた鐘撞き堂は、
大屋根部分が約10トンあります。

この屋根を4本の柱で支え、鐘の重みで安定させているそうです。
そんなお話も聞きながらの取材では、
四日市市川尻町の歴史についても伺いました。
「川尻」には地区を流れる内部川の終わりという意味があり、
町名の由来になっているそうです。
水害も多かったようで、
かつて正久寺の境内地は、今より300メートルほど北東にあったとのこと。
1659年の水害の後、高台を求め、
正久寺を含め全集落ごと移住したという歴史があるそうです。

住職の安田さんは、
1974年(昭和49年7月のゲリラ豪雨を経験していて
対岸の内堀町が水にのみこまれた惨状を目にしているそうです。
6月4日(水)の放送では戦争の話を取り上げますが
地域の歴史を知る貴重な時間でした。